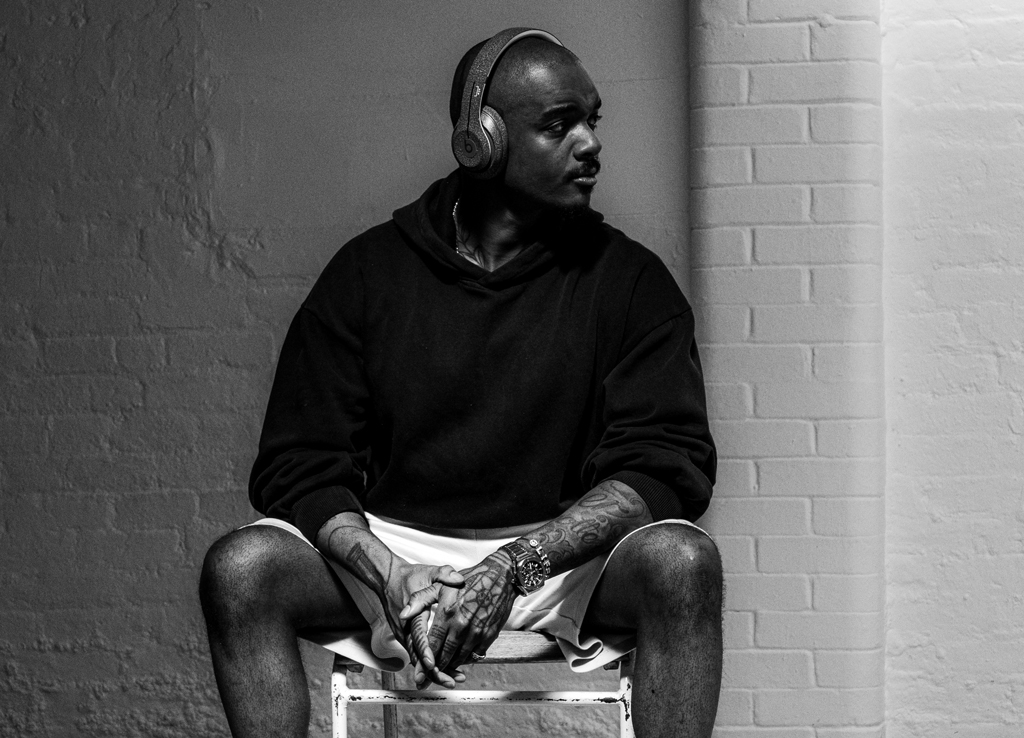INTERVIEW 2020.4.30
the Force
OMAR AFRIDI
暖かみのある洋服を
2019年のAWコレクションから、前身となるブランド、レオン・バラからオマール・アフリディへと名前を変え、新たなスタートを切った。ロンドンをペースに2 人の日本人がディレクションを務め、一歩一歩着実に歩みを道めるオマール・アフリディ。涜行のサイクルが目まぐるしく回る現状の中、クリエイションに向き合い洋賑から世界観を広げていく。彼らからは新たな、次の世代へとつながるようなファッションの可能性を見出すことができる。
※こちらはGRIND Vol.93に掲載した記事です。
Photo_ASUKA ITO

人と共存する要素
ロンドンの地で活躍する2人の日本人若手ファッションデザイナー、菊田潤さんと市森天颯さん。表面的な部分からも、どのようなブランドか興味を駆り立てられるが、肩書きだけでは終わらない彼らのクリエイションヘの姿勢やマインドがアイテムや世界観をさらに魅力的なものにする。「このブランドは、もともとレオン・バラとして3年間ほどロンドンをベースにして活動していました。2019SSシーズンから、市森がデザイナーとして参加することになりました。彼はもともと武蔵野美術大学で空問デザインを学んでおり、そこで縁があってレオン・バラの経営者であるオマールと出会い、2019AWシーズンから市森の友人でもあった自分が参加して、現在のブランドになりました。オマール・アフリディというブランド名は創業者の名前から取っています」。学生時代からの友人であった菊田さんと市森さんの2人がともに手がけていることが、ブランドとしての強みにもなっていく。「常にコンセプトの中心には“人”がいて。誰かが成し遂げたことや、人とともにある自然から刺激を受け、そこに対してより深いリサーチをしていきます。まだブランドとしての強みと言えるのか定かでないのですが、2人でやっているということ自体が大きな意味を持つと患います。僕たちがはじめて一編にモノづくりをしたのは4年ほど前で、そこから機会があれば製作をしてきました。モノづくりへのアプローチは全く異なるのですが、お互いの考え方に強く共嗚していたんです」。2人の異なるスタイルが、ひとつのブランドのクリエイションに落としこまれる。角度の違う興味や視点が、ぶつかり合いながら反応を起こし、根底にある共嗚する価値観をベースに構築されていく。

ローテクならではのかっこよさ
アイテムの風合いやシルエットから、はじめて見るような新鮮さと同時に、親しみにも似た感覚を覚える。「AW19コレクションからほとんどの生地を日本から仕入れています。以前のレオン・バラでは、合成繊維のテクニカルな生地を仕入れていましたが、改めてオマール・アフリディとしてやっていくタイミングで、日本の生地を使うことにしました。社会的にも情報が溢れ、ハイテク化が進むなかで、ローテクな部分にあるかっこよさへ共感しました。そして服を取り暮く環境を考えた時に、温かみのある服が作りたかったんです」。情報に溢れ、そのスピードに流されてしまいそうにすらなる現代において、温もりを持った拠り所となる洋服を生み出そうとするオマール・アフリディ。彼らのクリエイションの中心にある“人”というキーワード。“人”から派生する温度や人間味などを、物体としてではなく、空気まで捉えて発信していこうという姿勢が見えてくる。デジタルやハイテクの時代に欠けているように思える部分に価値を見出し、洋服に乗せて表現することで、ロンドンからじんわりと熱を帯びて人々に伝わっていくだろう。ファッションと人は切っても切り離せない、相互の関係性の上に成立していて、人生を豊かにするものがファッションであるなら、ファッションをより楽しめるものにするのは人の存在なのではないだろうか。忘れかけている本質にも近い部分を、表現したいことを追い求める過程で手にした彼らは、スタートしたばかりではあるが、さらなる勢いでその名を広めていくことになりそうだ。
ルーツとなる活動と出会い
今ではロンドンを拠点に活動する2人だが、そのルーツや歩んできた道のりは大きく異なる。(菊田さん)「僕は小中学校時代を日本で過ごしておらず、高校入学と同時に帰国しました。そのタイミングで古着と出会い、放課後は毎日のように入り浸ってました。中でも当時原宿にあった、メセンという古着屋が自分にとってとても新鮮で、個性の塊のような人たちを多く目にしていました。その当時からスタイリストに憧れていたのですが、自分なりにこんな服があったらと思うようになり、服を作りはじめて、ビジュアル作りまで含めた展示を行ったこともあります。この時が市森とはじめてモノづくりをした時でもあります」。(市森さん)「僕は母が服を作っていたことから影響を受けています。物心ついたころから、ミシンや裁縫道具が家にあり、ポタンを買いにニューヨークまで連れて行かれたこともありました。大学生になって自分がニューヨークに行ってボタンを買った時に、以前母が買ったものと全く同じものを買っていた時には、自分のルーツだと強く自覚しました。イギリスに興味を持ったのは父の影響です。器や陶芸や、ポタンなどの資材探しも好きで、バックパッカーをしていた時に、ヨーロッパを周り、ギャラリーを巡ったり、ポタンなどを買い集めてましたね。その経験が大学の卒業制作に大きく影響を与えました。結果として優秀賞をいただいて、オマールと出会うきっかけにもなりました」。製作における互いの役割も新しい形を提示している。「まず2人でコレクションのテーマを決めて、僕がテーマに沿ったアイテムとスタイリングを大雑把に構成し、市森に投げます。市森がパターンに起こしつつ細かいテクニックを乗せ、そこから2人でデザインを発展させていき、最後に僕がビジュアルに落とし込む流れですね」。持っている感度や得意な分野が違うからこそなせる技が、健康的な影響を与え、クリエイションにおける良い循環を生み出す。


19AWのショーに臨んだ際の様子。2ヶ月半という短い製作期間で、2時間のプレゼンテーションを作り上げた。コレクションテーマは「Pastoral Nomadism」。ブランドのオーナーであるオマールのルーツにある、遊牧民のライフスクイルに関心を持ち、リサーチを進める中でドローイングの要素にたどり着き、ショーの中でも表現されている。
求めていることを
共有できる仲間
温かみのある洋服、“人”を感じられるモノづくり、その方向性を一層強めるのが、コレクションの製作方法。多くのブランドが、きっちりと役割を分け、餅は餅屋というように製作を進めている。もちろんそれはクオリティを追求する上でのひとつの手段であり、実際に一般的に受け入れられている方法であるが、オマール・アフリディは斬新なアプローチを試みる。「コレクションの構成を一貫したチームで行い、各自の業種のポーダーを超えて動いています。カメラマン、スタイリスト、デザイナーがそれぞれの活動の範囲をまたいで提案し合うんです。全体の考えを共有しつつ、各自がリサーチなどを並行して行います。もちろん簡単なことではないのですが、数年来一緒にやっている仲間たちで、お互いが何を求めているのかある程度理解できています。業種というポーダーを超えたアプローチによって、コレクションが構成されていくんです」。馴れ合いではなく、気の知れた仲間たちが真剣に物事に臨むからこそ、実際に生まれたモノが評価されはじめている。そうした関係性は彼らのベースである、ロンドンという土地柄の影響もあるだろう。「ロンドンでは人と人のつながりがまた人を呼び、可能性を与えてくれます。この街自体が創作を楽しみ、それが文化として形成されているんです。ファッションやアートに対する熱量も年齢を問わず高く、かっこいいものはかっこいいと素直に思えて、素の感覚を飾らずに共有できるんです」。彼らの感性が風土とマッチすることで、より自由に、かつ前向きに取り組むことを可能にする。
オマール・アフリディのデザイナー、菊田さんと市森さんの2人は、前例がないことを恐れずにスタイルを貫き、もがきながらも前進して新たなモノと付随する世界観を作り出す。ストーリーを反映したアイテム作りと、そこから派生して出来上がる物語。オマール・アフリディはファッションを含むクリエイションにおける垣根、さらには人とファッションの間の境界線すらも曖昧なものにしていくような、次の世代への一歩を踏み出している。

三軒茶屋の古着屋、モールスで展示会を行った際の様子。その空間とブランドのアイテムが互いを引き立て合うような、ディレクションに。日本で認知を広めるきっかけにもなった。

ルック画像の1枚。2人が並ぶことで、ひとつの模様を描く服。コレクションの中心に常にある“人”のつながりや、ポーダーを超えてひとつの服となる機は、まさにプランドのコンセプトを象徴するようにも思わせる。
PROFILE
OMAR AFRIDI
蕎田潤さん、市森天颯さんの2人がデザイナーを務めるブランド。2019AWシーズン、前身のブランドであるレオン・パラからオマール・アフリディに名前を変え始動。ロンドンでのショーや日本での展示会が評価され、徐々に注目を浴びはじめている。さらなる躍進に期待が集まる、新進気鋭のブランドだ。