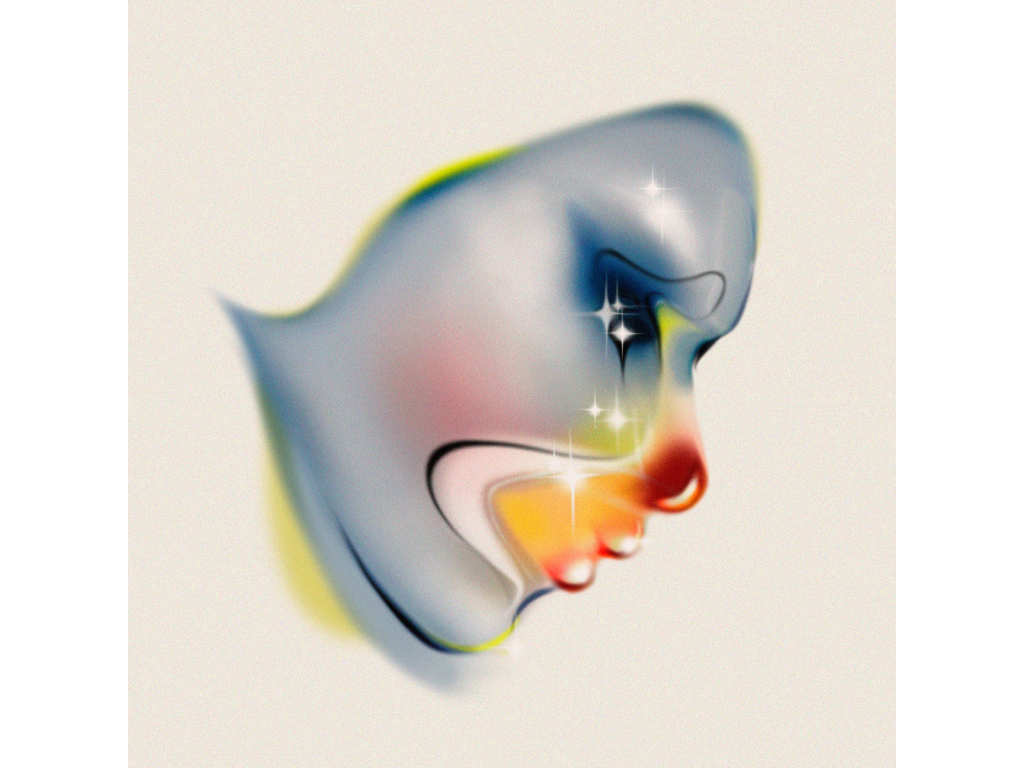FASHION 2020.4.30
the Force
Maison MIHARA YASUHIRO
芸術と対話し続ける
アティチュード
1994年、アレキサンダー・マックイーンが“モードの異端児”と評され、ファッション界のタブーを次々に打ち破り続けていたのと同じ頃、MIHARAYASUHIROの前身、アーキドゥームは産声をあげた。アバンギャルド全盛、突然変異的にドメスティックなブランドが次々と日本に誕生したのと時を同じくして。当時のある雑誌には“アバンギャルドな胸騒ぎ”のタイトルが躍っている。独学で靴を作りはじめ、右に倣えせず、独創性を貫き、走り続けた三原さんが、会社設立20年の時を経て、今思うこと。停滞するファッションの世界へ投げかけるアンチテーゼ、アバンギャルドであり続ける精神。『Fashionの力』、第1回にふさわしいブランドの“底ガ”を届ける。
※こちらはGRIND Vol.85に掲載した記事です。
Photo_TARO HIRAYAMA

『うち、破壊力あるから』
“20歳の時、芸術家を志し、東京の美術大学へ入学した僕は学生時代に靴を作ったことをきっかけに、思いもよらず華やかなモードの世界に足を突っ込んでしまいました。時代の荒波にもまれながらも会社を設立して、あっという間に20年という月日が流れてしまいました。よく「好きなことをやって生きて羨ましいね」と言われますが、全くその通りで、好きなことばかりやってなんとか生き残っています。これも皆さんの支えがあってのことです。本当にごめ
んなさい”。
会社設立20周年の節目に行われたショーのインビテーション、三原さんは直筆のメッセージを書いた。取材当日も靴の修理が完了したお客さんに添えるメッセージを書いていた。人との出会いを大切に、感謝する三原さんらしいー面。が、いつも見せる笑顔同様のその優しいハートとは裏腹に、脳はクリエイティブでアバンギャルドな細胞で動いている。
ショーの舞台は秩父宮ラグビー場、置かれたドラムセットから、会場にいる誰もが“ライブがはじまってモデルが登場する”イメージを先入観として植え付けられていた。ショーがスタートし演奏が始まり、大型のトラックが現れ、モデルが出てくると思った瞬間、けたたましくクラクションが鳴る。「もう勘弁してくれよ」とストレスが溜まったタイミングを見計らって、トラックのコンテナからモデルが一斉に現れる。三原さんが警備員の格好でモデルを誘導する。ガリアーノや、マックイーン、マルジェラが見せてきたような、既成概念をぶち壊す、痛快な、まさに“SHOW”だった。
「今回は東京でやることもあって、整ったショーの舞台でやるのはやめようと考えました。お金を使わなくても、おもしろいショーはできる。それを見せること。くすぶっている若い子たちにメッセージを発信したいと思ったんです。90年代に道端で僕らがやっていたようなわい雑なのが良いと。『うち、破壊力あるから、オンスケジュールと別にした方がいい』って無理言ってAmazon Fashion Weekから1 週間ずらしてもらって、『デリバリー遅れですみません!』ってメッセージで。何が今、ファッションは楽しくないと思わせているかって、情報ばかりが先に入ってきて、舗装された安全な道路をずっと走っているような感覚になっているからだと思うんです。荒れた道がない。パリもロンドンもどこも同じ。どこかで若い子たちに『そんなものぶち壊せ』ってところを見せたいと思っていました。ショーって情熱とか生き方とか熱量を届ける場だと思うんですよ。それはお金がなくてもできる」。

イノベーティブな精神
“アートを身近なものにする”。学生時代に抱いた野心は今も変わっていない。多摩美術大学でテキスタイルを学び、芸術を学んだアカデミックなキャリアの“イメージ”に三原さんはシンクロしようとしない。カウンターカルチャーを愛し、逆をつく。イノベーティブなものづくりにこだわり、アンチテーゼを投げかける。
「革に関しての話ですが、僕がまだ若い頃、豚の透明な黄革で靴を作っことがあったんです。牛革でも作ろうとしたけど、さまざまな要因があって、透明にはできず、そのときは諦めたんです。つい最近になってeccoが開発したと聞いて、すぐに連絡しました。革は人類の中で一番最初に起こったリサイクル、副産物なんです。肉を食用して出た動物の皮を捨てずに衣類にしたことが起源にある。アフリカの原住民を見れば未だにそれが続いていることがわかる。繊維業も皮革産業も斜陽産業と言われている時代ですが、僕らは、皮にはまだ可能性があると信じています。eccoはイノベーティブな意識を持った企業で、伝統とか過去にとらわれず革新をもたらそうとしている。西陣と組んだ時に細尾さんと一緒に仕事をしましたけど、細尾さんたちも同じで、伝統産業とは思えないほど新しいことに挑戦している。僕はそうした時代を切り開こうとする意思とか、イノベーティブであり続ける姿勢、思いを持った人たちに心を動かされる。僕もそうありたいから」。
MIHARAのDNA
“日常に創造性を纏う”。昨年、三原さんはスタッフが持つ名刺にメッセージを加えた。独学で靴を作りはじめた頃には想像もしていなかったほど、ブランドは大きくなり、スタッフも増え、三原さんは今、人を育てる立場にいる。
「大きなヴィジョンは持っていないけど、理想はあって、FITにしてもMYneにしてもMIHARAを理解していない子にやらせている。それは、MIHARAの形を変えたものを望んでいるのではなく、その世代なりの考えで自由にクリエイションしてほしいから。僕もブランドをはじめたのは23歳で、当時は右も左もわからないまま続けていた。なので、一旦は自分のDNAとかクリエイションの方法論やプロセスは徹底的に教え込みます。テーマに対してどうすれば血の通ったものづくりができるかとか、誰も気にも留めないようなことも。そういうことはいずれできるようになってくるんです。で、今度はある意味僕より僕っぼいものを作るようになる。でも自分のクローンは望んでいない。本人のアイデアを尊重し表現させる。無責任な言い方かもしれないけど、若い子は育てるより、無謀さにトライさせるべきだと思っています。以前はミハラヤスヒロってブランドは、僕の哲学で、それを具現化した世界と考えていた。あるブランドの若いデザインチームに、『リサーチをかけると必ずあなたのアーカイブが出てきます』とか『あなたに憧れてファッションの世界に入った』とか言われて、うれしいと思う反面、自分の論理がひとつ認められてしまった焦りも生まれた。何をやっても許されるような。昔はいつも賛否両論あって、火を焚きつけられたけど、否定が少しずつ減って。その壁を壊すのはチームの力なのかなと。今は育てることもひとつのクリエイションと考えています。コピー人間を作るのではなく、僕の論理や考え方を知ったうえで、何をするのか、その姿勢を見たい。それがいずれブランドに、ファッションに、新しい力を与えてくれるんじゃないかと思っているんです。
“日常に創造性を纏う”の意味は、人と芸術を調和させるという使命感から。芸術の本質は人を豊かにすること。人々に考える事を強要させることだと信じているからです。今は想像力よりも情報が優先されて、あらゆるものが視覚化された時代で、人がほとんど何も考えなくていい世界になっています。想像をさせない方が楽と考える人がいるからだけど、でも、それはとても不幸なことだと思うんですよね。芸術を説明できる人なんて本来いないんです。人の生活を彩り豊かにする。考えさせることが芸術の本質。僕らも人に“考える”を与え続ける会社にしたいという思いから、そのメッセージを常に持ち続けるという思いから」。
愛されるカ
「1回、いや、2回断ったのかな」。三原さんに靴づくりの基礎を教えた早川さんは出会った当時のことを思い出して、振り返る。「木型もなしで作った、巾着みたいな靴を持ってきてね。教える気なんて全くなかったんだけど、当時、三原くん、近くの問屋でアルバイトをしていて、朝1 度来て、掃除、片付けして、学校へ行って、また来てって、立川と浅草を毎日2 往復していたんですよ。その姿を見てるうち、強い意志というか不屈の精神のようなものを感じたんです。それで木型の作り方を教えるようになった。変なことをするのはもうわかってたから、木型も“甲から後ろはいじってはいけない”ってルールを与えたんですけど、ひとつ目に見せられたのがユニコーンみたいにトゥにツノの生えたやつ。『どうするの?作れないよ』って。そのあとも見たことないものばかり作ってきて、どうしようかと思ったけど、でも、そういう時って男気が勝つんですよね。僕も腹をくくつて「できないものはできないとはっきり言うけど、可能性があるものは作るから、なんでも持ってこいと。それがはじまり」。

多摩美術大学在学中に独学で制作したシューズ。「当時はジョン・ムーアに強く影轡を受けていました。作るごとに真似しちゃいけないなと思って、自分なりの考えを持ち込んで」。
三原さんは画家のお母さんのもとで日常的に美術に触れて育つ。「日常でダリやセザンヌの画集には触れられるのに、美術館に行くと『触ってはダメ』と怒られる。なぜそんなに崇高なものとして扱われるのか、大人になり理解はできるようになったけど、当時は違和感でしかなかった」。“アートと人を調和させる”、その思いで美大へ進んだ。
「何が芸術か線引きが難しい時代に、自分は何を定義するか?人が使って消費できるものを題材にしようと思った。そのアイコンが靴でした。椅子でもコップでもなんでもよかったけど、ガンプラで育った世代だから、だいたいのものは見れば設計図がわかる。でも、毎日のように使っているのに、どう作られているか靴はわからなかった。だから。常務(早川さん)もそうですが、当時いろんな人に会いました。平川武治さんに作った靴を見せたら、おもしろいと思ってくれて、栗野(宏文)さんを紹介されて、今度は栗野さんから『リンダ・ロッパに会っておいで』って言われてアントワープまで行ったり。ほかにも“会ったほうがいいリスト”を渡されて、ヨーロパには何度も行きました。無謀なことが世の中には必要だと自分自身感じていたし、会いたい人がいれば、勢いでも次の日に飛行機のチケットを取って行くくらいの覚悟と行動力がないと、世の中を変えることなんてできないと思っていた。今思うとよくやったなと思いますけど。みんなに励まされました。作家としてものを作って、世の中に何かを発表するということは少なからずメッセージであって、喧嘩を売ること。作らないとはじまらないし、ものがあってはじめて対話ができる。自分が作ったもので人と議論できることが何よりうれしかった。商業的に靴を売ることは考えていませんでした。ファッションの世界に入ったのは結果として、会う人会う人がファッションの人だったからです。ブランド名も栗野さんのアドバイスからなんです。『自分の名前でやるのがいいよ』と。でもYASUHIRO MIHARAはしつくりこない。そこに栗野さんが『日本人と外国人のファーストネームとファミリーネームの違いなんてこれからは誰でもわかると思うよ。逆にYASUHIRO MIHARAって海外に合わせること自体がオールドファッションで、日本人のメンタルの弱さを表していると思う」と。当時ファッションに関わっていた人はみんな西洋コンプレックスがあって、靴にしてもイタリアかイングランド、『メイドインジャパンは嫌』と扱ってくれないセレクトショップが当たり前の時代でした。日本人としてのバックボーンからくる哲学とか考え方、パブリック的な意味合いも含めて、栗野さんのひとことによってパズルがはまったような、全て解決した感覚がありました。感謝しかないです。20年これまでやってきて、YASUHIRO MIHARA にしておけばよかったと思うことは1度もないですから」。

中学、高校時代に着用していたライダースジャケット。スタッズの打ち込み、イラストやレタリングの手描き、すべて三原さん自身による。
なぜ三原さんは人に愛され、人を巻き込めるのか、長い間近くで見てきた早川さんは、その魅力をこう説明する。「彼、ニコッと笑うんだよね。それでだいたい許してもらえる。甘えん坊というか、人懐っこい、肩の力が抜ける顔をする。それでみんな気にかけるんだと思います。実際は頑固なところは頑固なんですけどね。いつもこれは作れる・作れないで言い合ってますから。ただ、すごいなと思うのは、どんなに売れたものも基本1回しか作らないこと。売れてるんだから、続ければいいと僕なんかは思うんだけど、『それは終わったこと』と言って切り替える。新しいことにしか興味がないんだろうね。それがMIHARAなんだね」。

三原さんの靴づくりの師匠であり、現在は常務を務める早川嘉英さんと、創業当時に撮影された写真と同じように並んで。
PROFILE
Maison MIHARA YASUHIRO
1996年、それまでアーキドゥーム名義で靴を発表していた三原康裕が自身の名を冠としてスタート。2000年より革を中心として服づくりをはじめ、同年に東京コレクションでショーにデビュー。2003年に会社名をSOSU とする。コレクションの場はミラノを経てパリヘ。2016年にブランド名をMaison MIHARA YASUHIROとしてリスタート。今年ブランド創設20周年を迎え、東京でもコレクションを発表。袖が4つのコート、足が4本のバンツなど、はじめた頃と変わらないクリエイションで世界を驚かせ続けている。