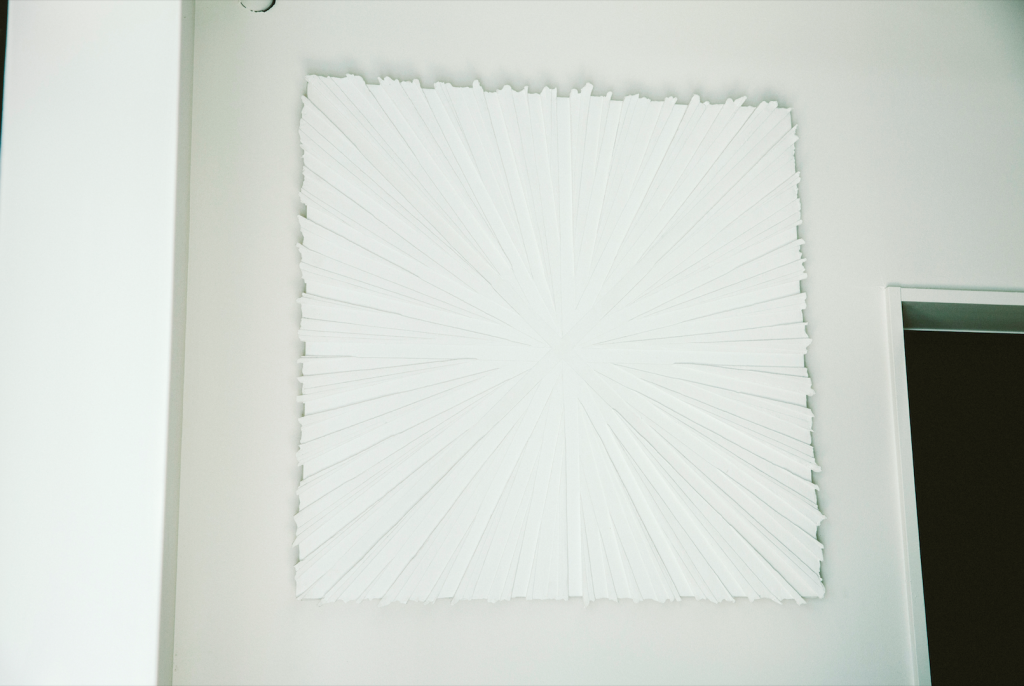INTERVIEW 2020.4.30
the Force
JOHN LAWRENCE SULLIVAN
貫かれる普遍の美学
「確実に勝てる試合ではなく、もっと刺激的な試合をしたかった。身を削るような」。約4年半前のインタビュー。荒士さんはボクサー時代のことを振り返り、そう答えている。ポクシングと同じように好きだったファッションの世界に1人進むことを決めて15年、荒士さんは今も変わらず挑戦し続けるスピリットを持ち続け、ファッションレーベルとして、ファッションと向き合い、勝負し続けている。テーラードを軸とするスタイルは何も変わっていない。〈ジョンローレンスサリバン〉、伝説のプロボクサーの名を冠に、強さと美しさを追求するブランドの、貫かれる美学、勝者のメンタリティに迫る。
※こちらはGRIND Vol.86に掲載した記事です。
Photo_ TAKAKI IWATA
自然体のクリエイション
善良と邪悪を意味する”dexter””sinister”の文字、漆黒と赤、デニムとレザー、テーラーリングとウェスタンディテール……。”PSYCHO KILLER”、”PSYCHOPATH”、映画『TwinPeaks』や『Taxi Driver 』からインスパイアされたニ面性を持った人物像から広がった、両極にある要素を組み合わせたコレクション。〈ジョンローレンスサリバン〉は今季も強い世界観でファッションの可能性を表現している。ショー形式で発表するようになって12年、ブランドを新鮮に映し続けるのは、変わらないブランドの軸とクリエイションの進め方の変化と発表の場の変化、意識の変化にある。「ブランドとしての軸はテーラリング。それは僕らの最大の武器であり、これからも変わらない。そこにエレメントが足されていく。結果的に今季はカウボーイっぼい要素。でもそれは作りはじめる段階ではぼやっとしていて、蓄積されたものが日を追うごとに少しずつリンクして、肉付けされて、変化していく。いいなと思ったものはなんでも混ぜちゃいます。テーマが固まるのは割と後の方。以前はテーマを決めてから作っていました。でもそのやり方はあるときに変えたんです。テーマを探して進めると、それにばかり縛られてクリエイションが広がらない。ショー形式で発表していると『テーマは?コンセプトは?』と聞かれることって多いんです。そのために、すごく偏ったことをやっていた。今振り返ってみると思うんですよ。例えばカジュアルなものは使わないとか、デニムなんて以前はランウェイショーで使うことはなかったし、フーディとかカットソーでルックを組むことなんてほとんどなかった。シャツを着せて、ジャケットを着せて、それを崩す。昔は今よりもテーマ性が強かった。今はもう少し振り幅が広いですね。アイテムということではなくて、ブランドとしてのアティチュードをコレクション全体を通してシーズン毎に感じてもらいたい。なんとなくですけど、広く見せていきたいというか、この前も誰かに『荒士が着ている感覚が1番かっこいいんじゃないの? 』って言われて。僕は結構崩して着るんですけど、パリで発表していた時ってかっちり型にはめようとしていたところがあったなと思ったんです。ファッション業界の人たちに、こう思われたいとか、いい評価を得たいとか、人を意識しすぎて発表していたようなところもありました。今はロンドンに発表の場を移して、楽しんでやれているような気がします。前も楽しかったけど、また違った感じの楽しみ方というか、プレッシャーを感じないでクリエイションできている。続けていく中で今は好きな人もいれば嫌いな人もいるっていう感覚が理解ができるようになりました。自分たち、やっているチームの中でベストなことができれば、結果はいい。ファッションって答えもないし、どこがゴールか見えづらい。その中で時代とマッチしたり、タイミングがくればムーブメントが生まれることだと思うところがある。でもそれを待つということではないですよ。チャレンジし続けていればいずれ未来が切り開かれるということ」。

ファッションの魅力
サリバンの強み
「子供の頃、新しいコーディネートを見つけたりすると純粋に気分が良くなることってありましたよね?みんながやらないようなことをやった時に感覚として理解できたときとか、自分の頭の中にすーっと落ちていくとき。そういうときって背筋が伸びているというか、人間的に自信をつけたと思う感覚になる。僕は洋服が好きで、運よく今もそういう気持ちを持てています。僕が作った服を手に取る人には、その感覚を感じてもらいたいと思っています。あんまり説明的にやっていくのはサリバンではない。サプライズであり、裏切りであり、常にエッジのあるもの。カッティングだったり、ディテールだったり、ものとして独特な部分だったり、自分が作る洋服は、視覚的なところで訴えかけるものでありたい。一瞬でハートに響くものとして。最近、海外誌で取り上げてもらうことが多くなってきたんです。強いエディトリアルにきっちりとはまっているのを見ると、スタイリストたちにとって、ファッションの可能性を広げられるブランドとして見てくれているのかなと、なんとなく思う。ミックスコーディネートして使われるのは率直にうれしいことで、独特な世界観のある服ではあるけど、組み合わせられる服だと思って作っているし、そう見てくれているのかなと。自分の作った服がスタイリストやフォトグラファーの感性を通して、自分で見てもフレッシュなものになって返ってくる。それを見れるのは今の自分の仕事のひとつのモチベーションです。モードの世界で仕事をしていて、ブランドとして目指す高みがある。そのときに、海外誌のオンシーズンの号に、自分の作ったものが載るのはとても重要なことだと感じています。有名なメゾンは当たり前に載る中で、でも僕らくらいのサイズのブランドで、そこに常に入り込めるブランドは数えるほどしかないから。そこに常に割って入っていけるブランドでありたいんです。ファッションヴィジュアルを見るのが昔から好きだし、ページを飾れることは純粋な喜びでもあるから」。

「基本的にアーカイブは残していない」荒士さんが、今も大切にする〈ジョンローレンスサリバン〉として初めて作った切りっぱなしのテーラードジャケット。15年経った今も古さを感じさせない、ぶれない哲学を感じる1着。
目指すべき高み
ブランドをはじめて15年、コレクションをスタートしてからで11年、インディペンデントな姿勢を貫きながら積み上げた認知。この先の目指す高みはどこにあるのか。
「はじめたころに若い世代に支持してもらえたことで、パリでコレクションを発表するまでのブランドに成長できたと思っているんです。15年が経過して、今また新しい世代の子がサリバンに興味を持ってくれている。ブランドとして次の世代につなげることができたというか、一世代に愛されて終わるブランドも少なくない中で、ひとつ波を乗り越えられた。ファッションでありモードを生業にするならば、若い世代に響かないと意味がないと思うんです。10代、20代の人も刺激し続けないと、その世界で存在し続けるのは難しい。あたり前ですけどデザイナーも歳をとる中で、でもブランドは老けないようにしないといけない。ファッションって買う側もチャレンジしなきゃいけないし、それに対して僕らは『こういうものを着たい』と思わせる服を作らなきゃいけない。少なからず意気込みを持たなくちゃいけない。世界に目を向けると、長い間残って、愛されているブランドって、やっぱり老けてないんです。作りはじめのころと変わらない気持ちを持って作り続けている。10年前、20年前のコレクションを見ても、今のコレクションを見ても、みんなアティチュードは変わっていないんですよ。自分たちもブランドのDNAとしてスタイルを貫き通して続けていきたい。商業的になって老けていくようなことなく、ファッションレーベルとして」。荒士さんのアイデンティティには失われないハングリー精神がある。それが若さを保つ力になり、若い世代のハートを惹きつけるのかもしれない。その精神はコアにありながら時代ともに変化し続けている。
「周りを見なくなりましたよね。東京で発表していたときはあったんです。東京で1番になりたいとか。今考えるとほんと小さなことなんですけど。今はもう全然気にならない。ショーのビデオも見返すことがなくなりました。リハーサルで見た段階でもう完結している。意識としてそこでもう次に切り替わる。マインドが変わったんですよね。毎シーズン、終わったら次、また次と。今は10年後にこうなっていたい、というような目標はなくて。毎シーズン、続けていくこと。それしか考えていないです。その延長線上で何か大きな出来事が生まれたらいい」。

ショップで働くスタッフとともに。
PROFILE
JOHN LAWRENCE SULLIVAN
伝説のプロボクサーの名を由来に、2003年に柳川荒士が設立したブランド。その名には強さ、風格、威厳すべてをファッションで表現しようとする思いが込められている。2007年春夏より東京コレクションに参加し、2011年秋冬からはパリメンズコレクションヘと発表の場を移す。2017年秋冬よりロンドンメンズコレクションヘ。スタート時から変わらず、メンズテーラードの技術を駆使したシャープな印象を特徴とする。