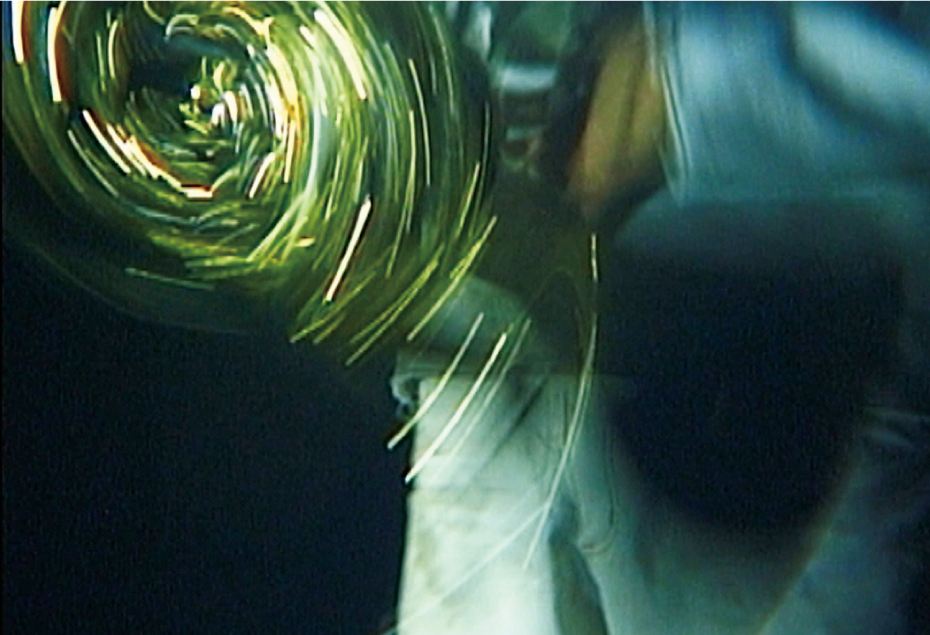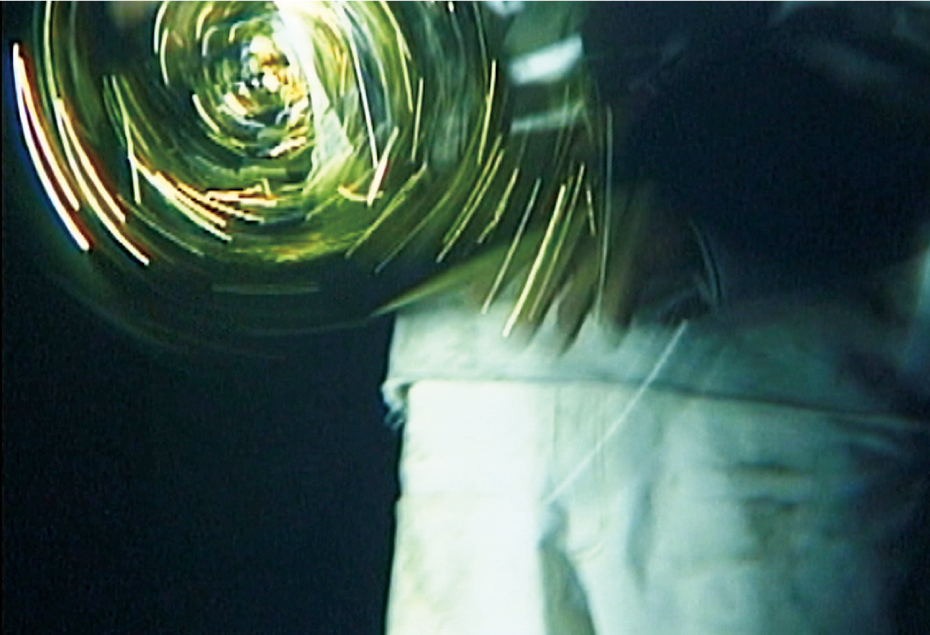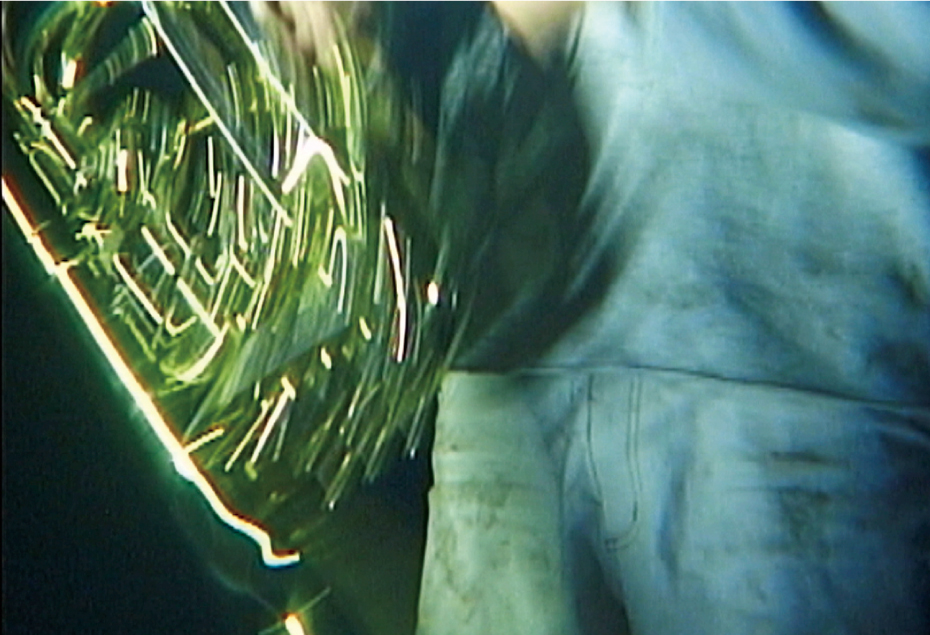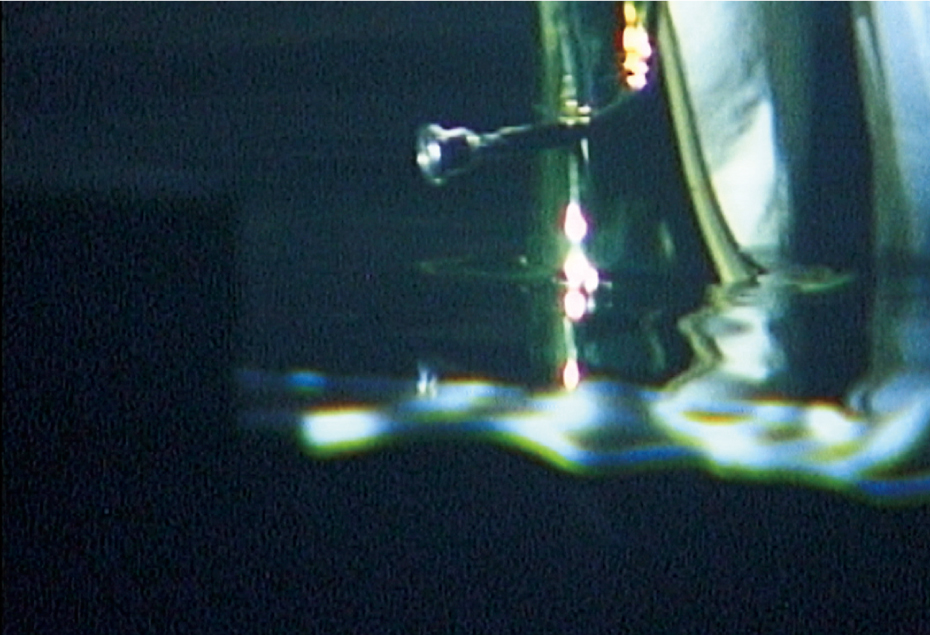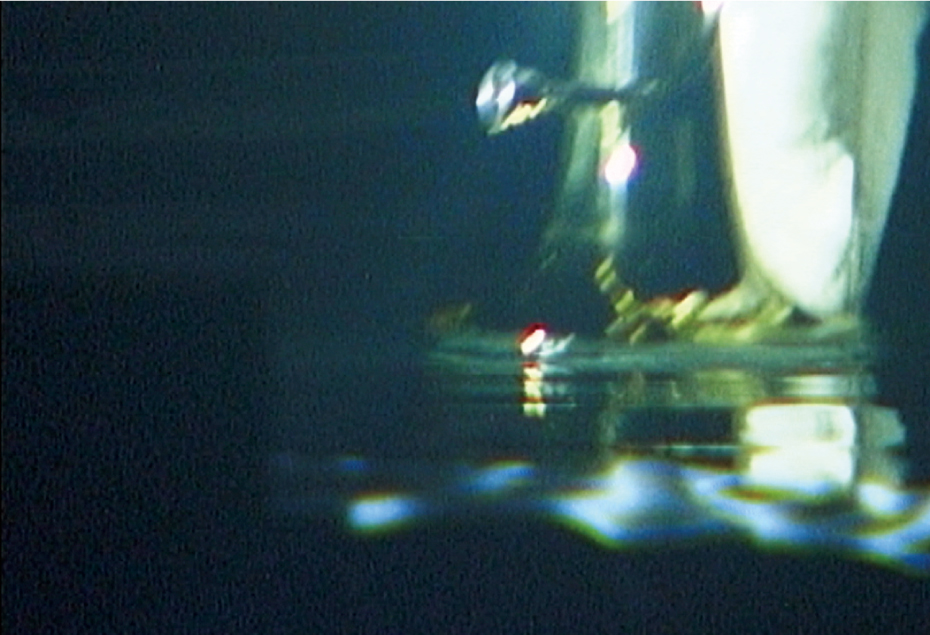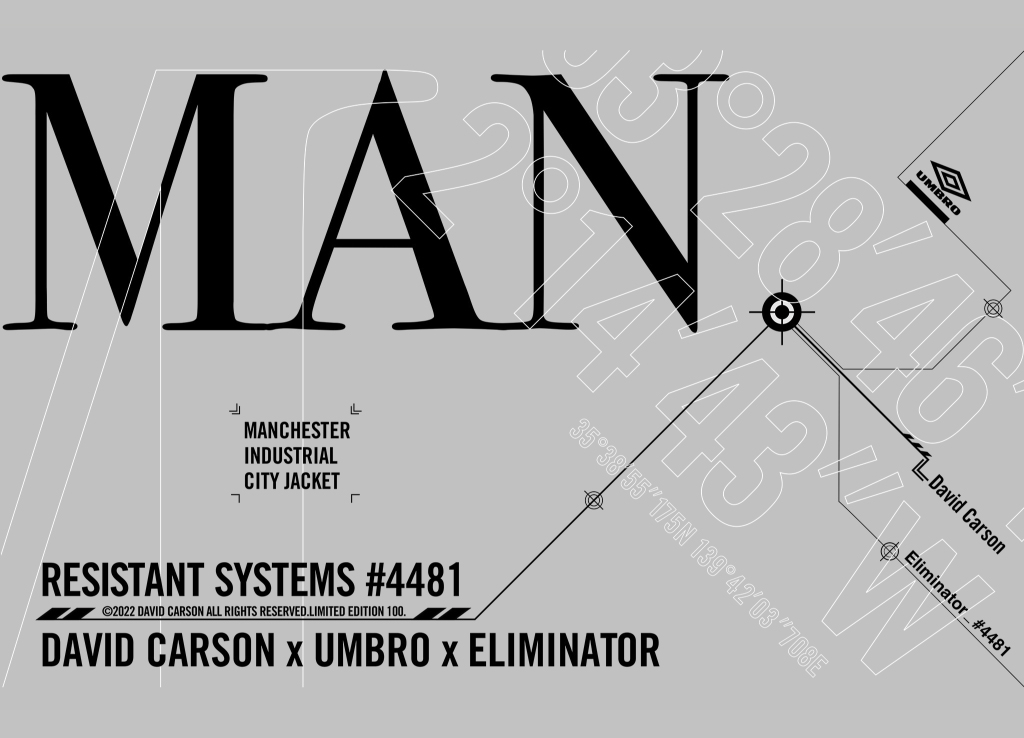CULTURE 2023.11.22
Berlin Atonal 23
Somewhere in between Reportage and Document
主観的で個人的な音楽体験を文字の配列である文章に置き換えて、どこまで伝えることが可能なのか。公式の映像監督が1秒24フレームの高画質の動画の隙間に漏れてしまうような瞬間を動画で記録し、静止画として提示することはどのような意味をなすのだろうか。ベルリンで開かれた音楽の祭典に参加して、体感した音像を誌面で叫び散らかすように痕跡を残すことは読者を挑発しうるのか。疑問と葛藤の間に揺れながら、個人の心象を映像の切り出しと文章で表出させる2023年『ベルリンアトナル』のレポート。そして10日間の熱狂後に行った主催者へのインタビュー。ルポルタージュとドキュメント、あるいは主観と客観のはざまから漏れ出すもの。
Still images Hiroo Tanaka
Edit & Reportage Hiroyoshi Tomite
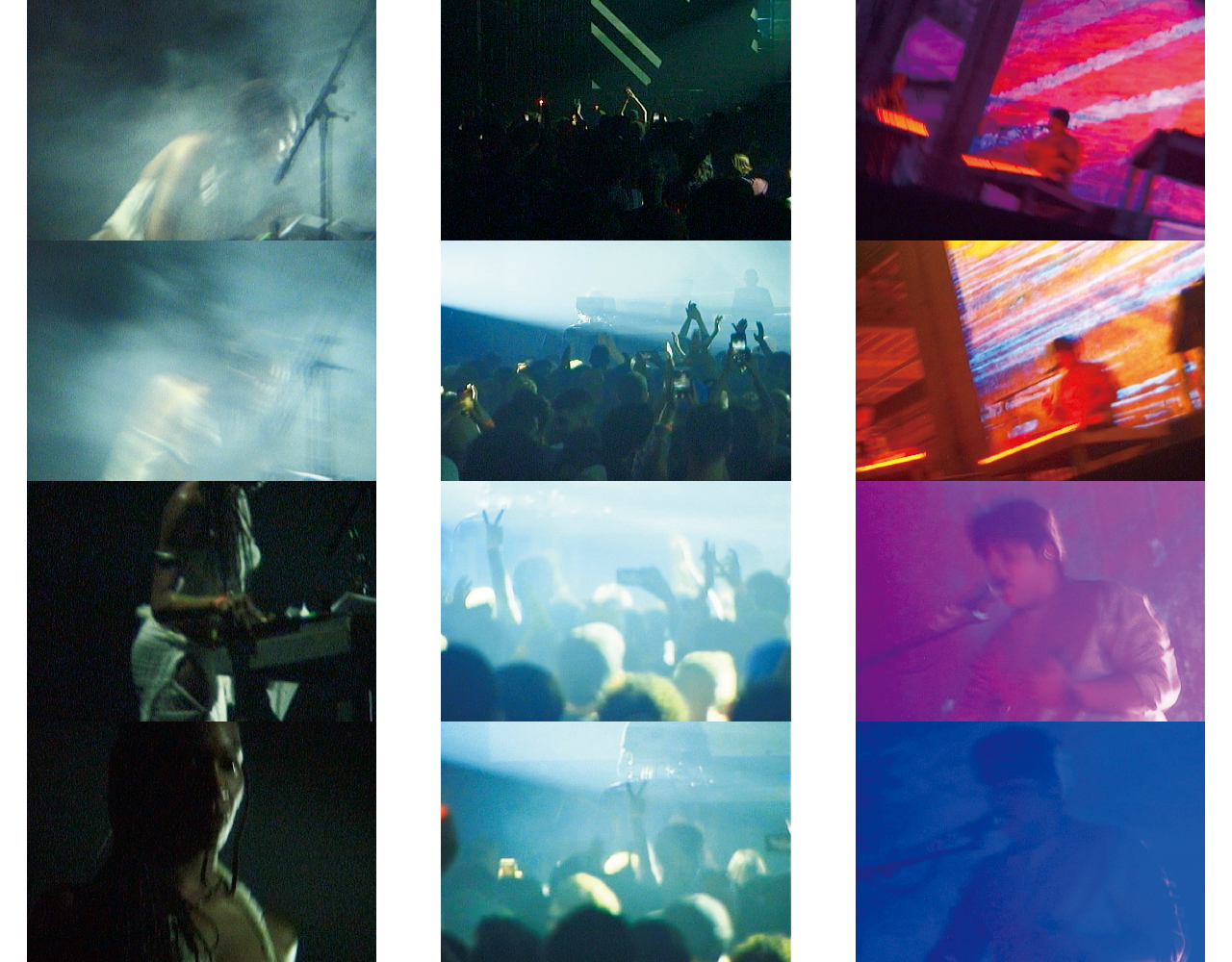
「公式映像製作をする10日間の中で高画質でのアーカイブ化と平行して行っていた、画素数をあげても映らない様な体験、24フレームの隙間に漏れていく様な瞬間を僕の思い入れのあるカメラたちでデジタルテープ上に記録しました。現場のアーカイブという行為の中で何時間もの高解像度の情報が電子メディアの中に記録されていく。200人以上が同時多発的に廃発電所の敷地内で表現をしている最中でカメラを回していました。その中の1秒24枚の写真に映された情報を、現場にいた僕はどれだけ認識できていたのだろうか?その隙間の時間で手に取ったのは思い入れのあるカメラ。僕が育った時代の情報源だったカメラたちによってデジタルテープに焼き付けるぼやけた世界の中で流れる時間は最新のカメラで写す瞬間とは違った類いの生々しい感触に溢れたものに見えました」
フロアに訪れた
ガイダンスを頼りに
ー 突如ハーネスをつけた裸体の女性達が空中からゆっくりと舞い降りる。パイプオルガンがけたたましく鳴り響く中、教会の鐘を打つパフォーマンスが繰り広げられる。ある時は地を這うような叫び声をあげながら、会場内でアーティストがのたうち回る。DJが流す体の芯まで揺さぶる音圧とノイズ。圧倒されて、会場に設置された長椅子に寝転ぶしかできなくなる。その時間すらも楽しんでる。
今振り返ってもあの強烈な体験は一体なんだったのか説明がつかない。思えば、3年以上前にベルリンに降り立って生活をはじめてから、このような理解の範疇を超えた音楽体験を熱望していたのだ。
2023年9月元発電所であるクラフトワークで催されたベルリンの音楽とアートの年に一度の祭典『Berlin Atonal(ベルリンアトナル)』。電子音楽を中心にアンビエントやドローン、ノイズ、エクスペリメンタル、グライム、ドリルなど次の時代を切り開く気鋭アーティストだけを200組以上そろえた宴は、メインストリームの潮流に飲み込まれることなく独自路線を貫いたにもかかわらず、10日を跨ぐ過去最大規模で幕を閉じた。エンタメの枠組みには到底収まりきらない過激で実験的なパフォーマンスを世界中から集った目と耳の肥えた観客と共に固唾を飲んで全身全霊で受け止めた。その断片を語る。
DAY1:
秘密のベールをはがすかのような、厳かなはじまりだった。トップを飾ったのはヨーロッパツアーを先駆けたLaurel Halo。どうやら通例アトナルのメインステージの1組目はワールドプレミア(世界公演の初演)という形式をとるらしい。以降も出演するアーティストはアトナル仕様のセットやこの日限定のコラボレーションのケースも多いのだ。それだけアトナルというものが耳の肥えた観客に支えられてきたのだろう。
ー 場を支配する異様な緊張感は、元発電所という特性とブルータリズム建築が醸し出す雰囲気がもたらすのだろうか。それともこの宴に対する過剰な期待からか。張り詰めた雰囲気をほぐすかのように、客演として呼んだチェリストの輪郭を作るようなサウンドとLaurelが奏でるピアノや電子音が生み出す朧なメロディが会場のスペースを埋めていた。リリース前のアルバム『Atlas』から繰り出される意識と無意識の間を漂うような幽玄な楽曲群を僕は不定形なリズムやメロディを辿るように体に染み渡らせるように受け止めていた。ーこれから2つの週末を跨いだ10日に渡る先鋭音楽の祭典が幕を開けるのだ。
胸ぐらを掴まれるように訴えてきたのがRainy Millerのパフォーマンス。未だ1stアルバムを昨年末にリリースしたのみで日本のリスナーにほとんど知られていないが、BlackhaineやSpace Afrikaとともに次世代のマンチェスター発の立役者になりつつあるラッパーだ。グライムやドリル、ダークなアンビエントを想起させるトラックにオートチューンに変換しても溢れるフローの柔らかでありながら切実な響き。ステージ外の会場をかけ回り、どこから飛び出てくるかわからない彼と直接的な映像も駆使したパフォーマンスは切実で衝撃と呼ぶほかなかった。時に体を痙攣させるように震わせながら、声を絞り出す姿は「今夜もまた自分を埋葬する」というステイトメントに違いのないものだった。オルタネイトな立ち位置でありながらも確実に次のUKラッパーの台風の目になる勢いを、見せつけられる瞬間だった。
メインステージのトリを飾ったのは先にあげたアンビエント・デュオ Space Afrikaと、キュレーターが変わってから幾度なく出演してきたベルリンベースのプロデューサー・トラックメーカーCaterina Barbieriのこの日限りのコラボパフォーマンス。アコースティクギターを片手にアルぺジオを爪弾きながら、アンビエントサウンドにビートやリズムのアクセントをつけていく。音と音の間をたゆたうようにしてステージ上を歩いていたのが印象的だった。セッションということもありラフな側面や余裕を残しつつ、しっかりと求心力のあるパフォーマンスをやってのけた。
やがて深夜零時を回るとTresorとOHMという2つの併設されたベニューが解放され、シリアスとも形容できるメインステージのパフォーマンスとは打って変わって、新しく訪れた客層とともにパーティの様相が増して、空気も客層も混沌と交わる。現在のクラヴシーンを牽引する多種多様なDJが、各々のアプローチでほとばしる観客の熱と呼応するようにパフォーマンスを繰り広げていた。
こうして10日にもわたって音と人の渦に飲まれて我を忘れ、朝日が昇るまでフロアをふらふらと回遊するのだった。朝が白む頃には聴いたことがないサウンドを過剰摂取した身体は、とうに限界を迎えており鉛のような重さにようやく気づく。耳鳴りと鳥の鳴き声と地下鉄の物乞いに包まれながら家路につく日もあった。あるときは勇んで朝6時に起きて、そんな人達と入れ替わりで、踊る日もあった。
Universal Metabolism:
週を跨ぐ形で平日に開催された展示イベント「Universal Metabolism」では、現代の資本主義を取り巻く状況に懐疑の視点を投げかける作品群が数多く展示され並んでいた。芸術が、経済原理に消費されることを拒むような即興性のあるパフォーマンス。矛盾を構造化して示すビデオやインスタレーション作品群が印象的だった。
とりわけ、パフォーマンス・アーティストBilly Bultheelが仕掛けた『The Thief's Journal』では、現代作曲とヨーロッパ中世・ルネサンス期のポリフォニック音楽の技法や伝統との架け橋となるような演奏とインスタレーションを探求しているように映った。浅いプールのような水面を舞台として用意し、背後には2枚の金属板。プールの上にドラム、小さな階段の上に管楽隊が鎮座する。9人の小さな楽団は周囲を回遊しながら歌い、鳴らし、パフォーマンスをしていく。規格外のパフォーマンスにただただ、目を凝らすことしかできなかった。まだ定義される前の芸術の姿がそこにあった。
Highlights:
メインステージ以外で特に印象的だったのは、2週目に日本から招致された「¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U」。基本的には電子音楽の祭典であることは間違いないのだが、彼がこの日流したのは、前回CTMフェスティバルでプレイしていた高速なハードコアテクノとは打って変わって90%ノンエレクトロ。クラシックやピアノソロなど幾重にもジャンルを横断したのちに、坂本龍一トリュビュート的な印象が強い楽曲を散りばめていた。後半ラスト30分となったところ『Merry Christmas, Mr. Lawrence』を流し会場の雰囲気を掌握していた。ただひたすらに音楽のみで、観客をどこかに誘い高揚させる。この伝説的であろう光景を見逃すまいと、下手のスピーカー側で一身に音を浴びながら彼をまじまじと見つめていた。するとふと気がつけば、近くには前号で取材をさせてもらったベルリンのレジェンドプロデューサーMark Reederが手招きしていた。近くに行き肩を抱き合いながら今目の前の音楽を浴びている喜びを分かち合った。特に多くの言葉を交わしたわけではない。しかしそこにこそ、魅了されてやまない純粋な音楽体験があったのだ。
ー スピーカーを前にして、目の前に広がった世界に身を委ねている時に湧き上がる、言葉以前の感情を全身全霊で受け止める。その体験をそばにいる人と分かち合うこと。あるいはそっと一人胸にひめること。その断片を普段の生活に記憶として持ち帰ることで、次の人生の選択肢と想像力を無意識のうちに確実に拡張しているのだから。